「AIって結局、何ができるの?」
今、多くのビジネスパーソンや副業初心者が抱えるこの疑問。
ChatGPTの登場以来、AIは一気に身近な存在になり、日常生活や仕事の中で使われる場面が急増しています。
けれど、「AIってすごいらしいけど、実際どんなことに使えるの?」と具体的なイメージを持てない方も多いのではないでしょうか?
この記事では、今のAIにできること・できないこと、業界別の活用事例、そしてこれからAIがもたらす未来まで、わかりやすく解説します。
この記事を読めば、「自分には関係ない」と思っていたAIが、あなたの仕事や生活にどう活きるのか、きっと見えてくるはずです。
AIとはどのような技術?

正直、初めて「AI(人工知能)」と聞いたとき、「ロボットのこと?なんだか難しそう…」と感じた方も多いのではないでしょうか。
私自信も、最初はSF映画の世界の話だと思っていて、自分の生活や仕事には関係のない遠い存在だと思っていました。
ところが今では、私たちが日常的に使っているスマートフォンや、ネットショッピングのおすすめ機能、さらには病院の診断支援まで、あらゆる場面でAIは活躍しています。
つまり、「AIとは何か?」を知ることは、これからの社会を生きていくうえで欠かせない教養になってきているのです。
 もりんさん
もりんさん私、機械音痴だからな~とのんきに言ってられない時代になってきたのです!
ここでは、そもそもAIとはどんな技術なのか、人間との違いはどこにあるのか、そしてその仕組みについて初心者でもわかるように、ざっくり解説していきます。
AIと人間の違いとは?
AI(人工知能)と人間の最大の違いは、「感情」や「常識」を持っていないという点です。



AIに恋愛はできないってことです。
たとえば、人間なら相手の顔色を見て「今日は元気なさそうだな」と空気を読みますが、AIはそういった“察する”力を持っていません。
AIは、与えられた情報に対してルールやパターンに基づいて判断をするのが得意です。
逆にいうと、情報がなければ、何も判断できないという弱点もあります。
実際に私が初めてChatGPTを使ったとき、うまく質問できずに「なんだか思った答えと違うな…」と感じました。
でも、言い方を少し変えてみたところ、驚くほど的確な回答が返ってきてびっくりしました。人間との会話と違って、“伝え方”にコツがいるのです。
人間は感情や直感をもとに物事を判断しますが、AIは計算とデータをもとにしか動けません。
だからこそ、AIは大量のデータ分析や処理が得意で、人間には難しい計算作業をあっという間にこなしてくれるのです。
AI=人工知能の仕組みってどういうこと??
たとえば、AIに「猫の画像」をたくさん見せて学習させると、「これは猫かどうか」を判断できるようになります。これを「機械学習」と呼び、AIの中心的な技術です。
さらに最近では、「自分で特徴を見つけて学習する」ディープラーニングという高度な手法も使われています。
このようにして、AIは少しずつ“賢く”なっていきます。
ただし、これは「人間のように考えている」というわけではなく、「たくさんの例をもとに、ルールを見つけ出している」だけです。
最初に私がAIの仕組みを知ったとき、「あ、だから答えが毎回ちょっとずつ違うんだ」と納得しました。AIは過去のデータから“予測”をしているので、完璧ではありませんが、それでも十分すぎるほど実用的だと感じました。


今のAI(人工知能)にできることって何?
にできることって何?-1024x538.png)
にできることって何?-1024x538.png)
AIってまだ未来の話だと思っていたけれど、実はもう身近なところでたくさん使われています。
最初はちょっと難しそうだなと思っていた私も、実際にAIを使ってみて、「こんなことまでできるの!?」と驚いたことが何度もあります。
ここでは、今のAIがどんなことに使われているのかを、具体的に紹介していきます。「あ、これなら私も使えるかも」と思えることがきっとあるはずです。
文章生成(ChatGPTなど)
まず、多くの人が身近に体験しているのが、ChatGPTなどを使った文章生成です。
たとえば、「SNSに投稿する文章を考えて」「ブログのタイトルを10個出して」とお願いすると、ほんの数秒でAIが提案してくれます。
私も最初は半信半疑でしたが、実際に使ってみると、そのクオリティの高さにびっくりしました。私のプロンプト(命令)がとってもよかったのかもしれませんが!
「思っていたよりずっと自然!」というのが率直な感想です。もちろん、完璧ではないけれど、アイデア出しやたたき台としては、ものすごく便利だと感じています。
最近では、メールの返信文や企画書の下書きをAIに任せている人も増えていて、文章を書くことに苦手意識がある人にとっては、かなり心強い存在になっています。
画像・動画の自動生成
AIは文章だけでなく、画像や動画も自動で作ることができます。
たとえば、キーワードを入力するだけで、イラスト風の画像やリアルな写真風画像を生成できるサービスがあります。
プロンプト次第で人間の創造を超えた画像をつくってくれます。私もmidjourneyをつかっていますがアイデア次第でいろんな画像を出せます。
ちょっとセンスのある人だと、人が考え付かない画像を生成して動画にし、アカウントをつくってバズらせています。
このAI画像はまだまだ伸びるジャンルだと個人的には感じています。
音声認識・翻訳・要約
音声をテキストに変換したり、外国語を翻訳したり、長い文章を短く要約したりするのも、今のAIの得意分野です。
私が初めて「これは便利!」と思ったのは、会議の録音をAIが自動で文字起こししてくれたときです。
これまでは1時間の録音を聞き直して手作業で文字に起こしていたのが、数分で終わってしまったんです。しかも、かなり正確。
また、英語の文章を自然な日本語に訳してくれるAI翻訳も使ってみましたが、「え、これ本当に機械が訳したの?」と思うほど滑らかで、昔の翻訳ツールとは全然違いました。
時間と労力の節約になるだけでなく、気持ち的にもすごく楽になります。
データ解析と予測
ビジネスの現場では、AIによるデータの分析や未来の予測がすでに多く活用されています。
私もECサイトの売上データをAIに分析させたことがあるのですが、「こんな時間帯に売れてたの!?」という意外な発見がありました。
いやあ、自分の脳みそだけでは到底わかならなかったことがAIを使えばわかっちゃうんですからすごいですよね。
難しい統計の知識がなくても、こうして自分のビジネスに役立つヒントを得られるのは、本当にすごいなと思いました。
ロボット制御と自動運転
少し専門的になりますが、AIは自動車の自動運転や、工場のロボットの制御にも使われています。
道路状況を判断して自動でブレーキをかけたり、工場で細かい作業を正確にこなしたりと、まさに「AIが目や耳の代わりをしている」という感じです。
私自身、自動運転車に乗ったことはありませんが、ニュースや映像で見るたびに「これが当たり前になる未来も遠くないのかも」と感じています。
実際に海外では自動運転の実証実験が進んでいますし、日本でも一部地域ではAIを搭載したバスの運行が始まっています。
「AIがハンドルを握る」なんてちょっと怖く感じる部分もありますが、事故のリスクを減らせるという点では、大きなメリットがあると思います。
AIにできることの具体例
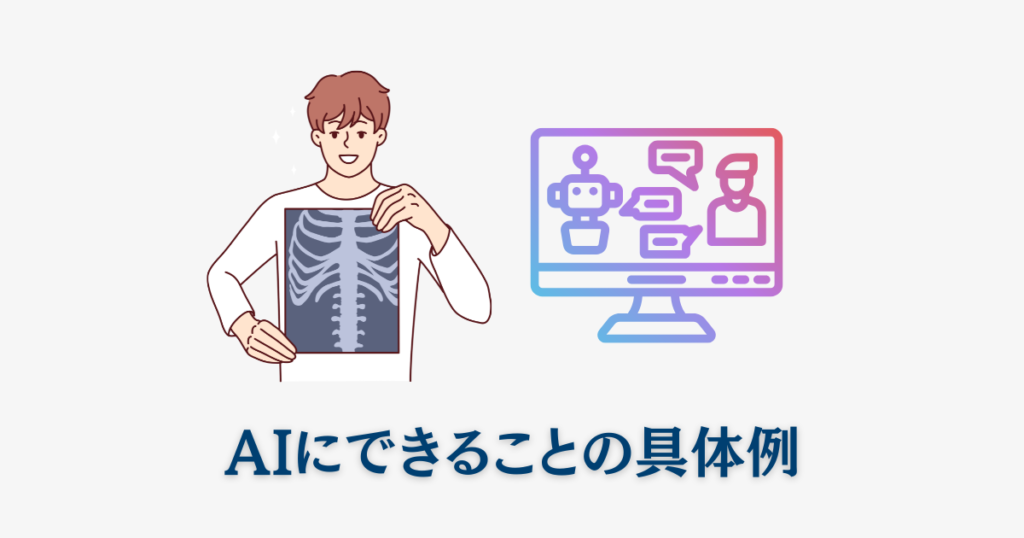
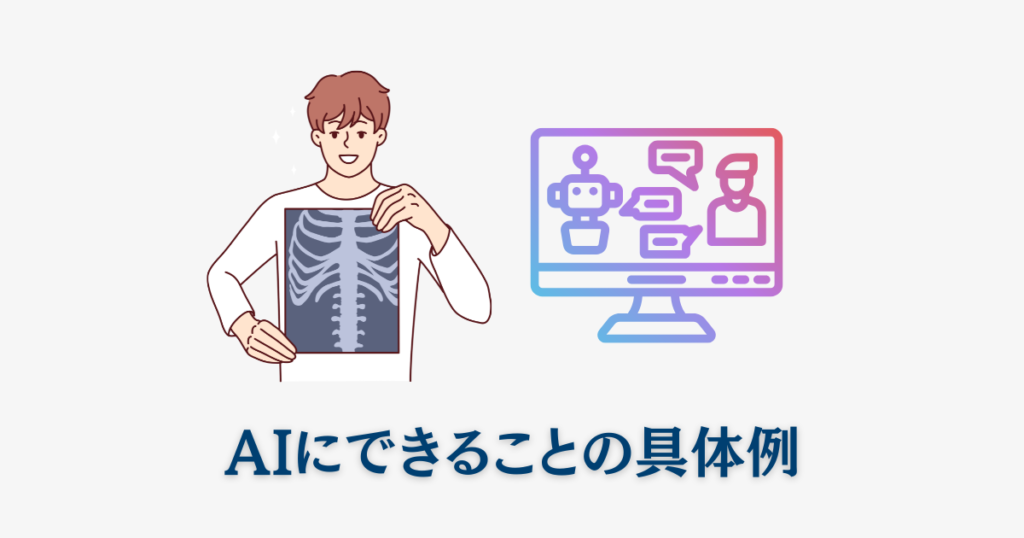
AIと聞くと「すごそうだけど、どこで使われてるの?」と思う人も多いかもしれません。
私もそうでした。でも実は、すでに私たちがよく使っているサービスの裏側で、AIは大活躍しています。
ここでは、AIが私たちの生活をどんなふうに支えてくれているのか、実際の例を交えて紹介していきます。
お店の問い合わせに自動で答えてくれるチャット
ネットショップや企業のホームページにある「ご質問はありますか?」というチャット画面。
あれも、AIが活躍している場面のひとつです。
私も、ネットで買い物をしていて「返品ってどうすればいいんだろう?」と疑問に思ったとき、問い合わせフォームに打ち込んだら、すぐに答えが返ってきてびっくりしました。しかも、的確で早い。夜中だったのに、すぐに解決できて助かりました。
こうしたチャットボットのおかげで、企業側も人手をかけずに24時間対応ができるので、お互いにとって便利な仕組みだと感じます。
「この商品どう?」とおすすめしてくれるAI
ネット通販や動画アプリなどで、「あなたにおすすめ」と表示される機能がありますよね。
私の場合、ネットでカフェグッズを何回か検索していたら、いつの間にか関連商品ばかり表示されるようになっていました。
最初は「なんでわかったの!?」とちょっと驚いたのですが、見ているうちに「これ欲しいかも」と思う商品に出会えて、まんまと購入してしまいました(笑)。
このように、AIはユーザーの行動を分析して、最適なタイミングで提案してくれるので、マーケティングの世界では欠かせない存在になっています。
動画編集が面倒なときにAIが自動でまとめてくれる
YouTubeやTikTokなど、動画を作って投稿する人が増えていますが、「編集作業が大変すぎて続かない…」という声もよく聞きます。
そんなときに便利なのが、AIによる自動編集機能です。
実際に私も、旅行の動画をスマホで撮りためたはいいけど、「編集しよう」と思ったまま1週間放置…。
そんなとき、AI動画編集アプリを使ってみたら、写真や動画を自動でつなげて、BGMまでつけてくれたんです。クオリティも思っていた以上で、そのままSNSに投稿できるレベルでした。
編集スキルがない人でも、気軽に動画発信ができる時代になったんだなと実感しました。
病院でAIが医師のサポートをしてくれる時代に
最近では、医療の現場でもAIが使われ始めています。
私は健康診断のときに「AIが入った診断システムを導入しています」と説明されて、「そんなところにもAIが使われているのか!」と驚きました。
もちろん最終的な判断はお医者さんがするのですが、AIが補助することで見落としが減ったり、診断が早くなったりするそうです。
命に関わる現場だからこそ、AIの力を借りて安全性が高まるのはとても心強いなと感じました。
AIができないこと・苦手なこと


AIがすごいスピードで進化して、「もう人間の仕事はいらないんじゃない?」なんて声も聞こえてきます。でも実際には、AIにはまだまだ苦手なことがたくさんあります。
私も最初は「AIって何でもできるんじゃないの?」と思っていたのですが、実際に使ってみると、「あれ?そこはできないんだ…」という場面に何度も出くわしました。
ここでは、AIがまだ苦手としている部分や、人間との決定的な違いについてお話していきます。「だからこそ、AIと人が協力することが大事なんだな」と気づくはずです。
感情や共感をともなう判断
AIはたしかに、知識や情報をもとに答えを出すのは得意です。でも、「相手の気持ちを想像して、やさしく声をかける」といった、感情や共感をともなう判断はできません。
たとえば、友人が落ち込んでいたときに「大丈夫?」と声をかけたり、言葉を選んで励ましたりするのは、人間にしかできないことだと思います。
実際に、私がChatGPTに悩み相談をしてみたことがあります。答えは丁寧でしたが、どこか「機械的」な印象が残りました。悪くはないけれど、「気持ちに寄り添ってくれている感じ」はあまり感じられなかったんです。
やっぱり人の気持ちに寄り添うには、心が必要なんだと実感しました。
常識に基づいた柔軟な対応
人間なら「こういうときは普通こうするよね」という“暗黙の了解”がありますよね。でも、AIにはその「常識」というものが通じません。
以前、AIに「雨が降りそうな日のおすすめの服装は?」と聞いたら、スーツやワンピースなど、季節や気温を無視した答えが返ってきてしまいました。たしかに雨とは関係あるかもしれないけれど、なんだかピントがズレていて、思わず笑ってしまいました。
AIは与えられた情報に忠実すぎるがゆえに、柔軟な判断が苦手なんです。人間なら、その場の空気や状況に応じて判断を変えることができますが、AIは“融通がきかない”ことが多いと感じています。
予測できない状況での判断力
AIは、あらかじめ学んだデータの中でなら、とても正確に動きます。でも、想定外のトラブルや初めての出来事が起きると、とたんに判断できなくなってしまいます。
たとえば、突然の事故や災害など、人間でも戸惑うような緊急事態では、AIは「こんなケースは知らない」とお手上げになってしまいます。
私は以前、AI翻訳を使って海外の人とやりとりをしていたのですが、相手が絵文字やスラングを多用したメッセージを送ってきたとき、AIはまったく意味を理解できず、完全に訳がおかしくなってしまいました。
想定外の事態に強いのは、今のところやっぱり人間の判断力だと思います。
AIにできないことの具体例


AIは便利だけれど、何でもできる万能な存在ではありません。実際に「これはAIにはまだ無理だな」と感じることも多くあります。
ここでは、私自身が実感した、AIでは難しい“人間ならでは”の活動や仕事について、具体的に紹介していきます。
芸術の“感動”を生む創作活動
最近では、AIが絵を描いたり音楽を作ったりすることもできます。確かに見た目や音は美しくて、「すごいな」と感じることもあります。でも、「心が動く作品か?」と聞かれると、私はちょっと違うと思いました。
私はAIが描いた絵をSNSで見て「きれいだな」と思ったことがありますが、それが誰かの人生の経験や感情から生まれたものではないと知った瞬間、どこか物足りなさを感じたのです。
やっぱり、人間の想いが込もった作品には、AIには作れない“深み”や“感動”があります。
子どもの教育やカウンセリング
子どもと接するときって、単に知識を教えるだけじゃなくて、表情を読み取ったり、声のトーンを変えたり、気持ちに寄り添ったりすることが大切ですよね。
私は子育て中の友人から、「子どもの気分がコロコロ変わるから、マニュアル通りにいかない」とよく聞きます。こうした柔軟な対応は、今のAIにはとても難しいです。
また、カウンセリングのように“人の心”を扱う場面では、ただ答えを返すだけでは意味がありません。心の温度を感じて、沈黙を大切にするような対応は、人間にしかできないと感じています。
倫理的判断が求められるシーン
たとえば、「この医療を続けるかどうか」や「災害時に誰を優先するか」といった、命や人権に関わる判断は、とても複雑で、正解がひとつではありません。
AIは過去のデータをもとに最善の“選択肢”を提示することはできますが、「それが正しいのか?」を判断するには、人間の価値観や倫理が必要になります。
私は以前、AIに「○○をするのは道徳的に良いこと?」と聞いたところ、答えは返ってきたものの、どこか他人事のような印象を受けました。やはり、人間がその場その場で責任を持って判断することの重要さを改めて感じました。




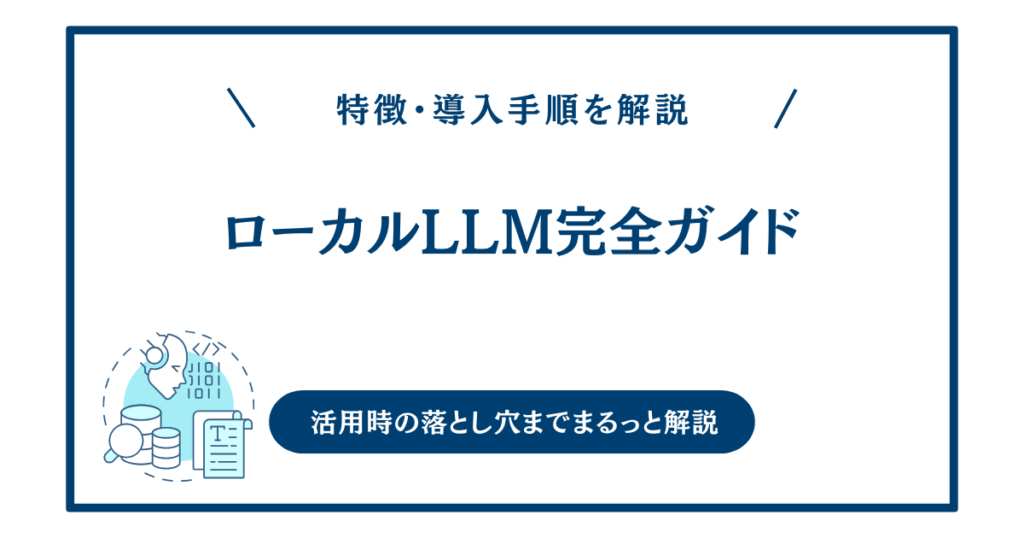





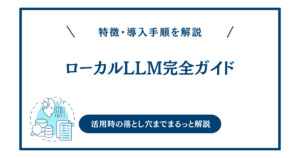


を使メリットとデメリットを実際AIを使いまくった私が徹底解説していきます!-300x158.png)


を勉強するには?-300x158.png)
