動画を作ってお金に変えたいなら、まず最初に気になるのが『商用利用できるかどうか』ですよね。
DeeVid AIは高画質な動画を簡単に生成できることで話題ですが、使った映像をSNSやYouTube、広告案件などで『実際に収益化してOKなの?』と不安に感じる方も多いと思います。
DeeVid AIは有料プランに加入していれば、作成したコンテンツを商用に使うことが明記されています。
この見出しでは、商用利用に関する基本ルールや注意点をわかりやすくお伝えします。

結論DeevidAIでつくった画像や動画でマネタイズは可能です!
\無料クレジットプレゼント中!今なら動画が無料で生成できる!/
有料プランのみ商用利用が可能


まず大前提として、DeeVid AIで作成した動画を商用利用できるのは『有料プランに加入している場合のみ』です。Lite、プロ、プレミア、どれも商用利用可能です。
登録直後には初期クレジットがプレゼントされるので、誰でも無料でツールを試すことができます。
でもこのクレジットはあくまで『体験用』。
商用での使用はできず、規約上も『非営利目的』での利用に限られています。
例えば、SNSにアップしてフォロワーと楽しむくらいなら問題ありませんが、企業案件や収益目的の配信には利用できません。
有料プランに加入することで、はじめて『商用利用可』というライセンスが得られます。
私も最初は無料クレジットでお試しして「これはいける」と確信してから、有料プランに切り替えました。
動画の質が高いから、安心して使いたくなったんですよね。
無料プランは個人利用限定で商用NG
先ほど少し触れましたが、無料プランにはいくつか制限があります。
その中でも大きなポイントが『商用禁止』です。
つまり、DeeVid AIで無料で作った動画を使って、商品を売ったり、サービスの宣伝をしたり、収益を得たりする行為は基本的にNGということ。
誤って商用利用してしまうと、最悪の場合、規約違反としてアカウント停止などのリスクも考えられます。
『ちょっとぐらいならバレないかも』という気持ち…分かりますが、やっぱり安心して使いたいですよね。
そういう意味でも、真剣に活用したい人には最初から有料プランをおすすめします。
日本語プロンプトは非推奨だけど画像・映像には利用OK
DeeVid AIは中国発のAIツールなので、どうしても英語ベースの設計になっています。
そのため、日本語のテキストやプロンプトで動画生成をしようとすると、意図しない表現になったり、うまく動作しないことがあります。
ですが、これはあくまでプロンプト(テキストの指示)上の話。
生成された動画自体に日本語を組み込んだり、日本語ナレーションを後から合成するのはまったく問題ありません。
つまり『日本語で使いたい』という方も安心してくださいね。
ただ、ナレーションや字幕など日本語を使う場合は、事前に外部で作成してから組み合わせるとスムーズです。
生成した動画の著作権はユーザーに帰属
ここが一番気になるポイントかもしれませんね。
DeeVid AIで生成された動画の権利は、ちゃんと『利用者(あなた)に帰属』すると公式に明記されています。
つまり、自分が生成した動画は自分の所有物として扱えるということ。
商用での使用も、再編集も、他のプラットフォームへのアップロードも自由です。
ただし、元の画像素材やテンプレートなどに第三者の権利が含まれていないことが条件。
一般的な使い方なら問題ありませんが、万が一『外部から読み込んだ素材』を使う場合には、その著作権にも注意してくださいね。
\無料クレジットプレゼント中!今なら動画が無料で生成できる!/
DeeVid AIで商用利用できる!
まず、有料プラン加入者なら、生成した動画は「自身のビジネスに使ってOK」です。
そのため、新商品をPRするショート動画をSNSに投稿して集客したり、YouTubeで広告を入れて収益化したり、Web広告に組み込んだりしても問題ありません。
たとえば、オンラインショップで新商品の特徴を説明する短いデモ動画を生成して、それを広告に使えば、広告費以上のリーチや売上につなげることもできます。
また、社内向けの教育用動画やプレゼン資料に組み込んで使えば、研修効率の向上や資料の質の底上げにもつながります。
AI生成だから「何でもOK」ではない!注意すべきポイント
ただし、「商用利用OK」とはいえ、すべての使い方が自由自在というわけではありません。
まず、著作権で保護されたキャラクターやブランドをプロンプトに使うと、生成された動画も著作物の侵害に該当する可能性があります。
たとえば、有名アニメキャラや商標付きの商品画像を素材にして商用に使ってしまうと、法的トラブルに発展しかねません。
また、「生成動画をそのまま売り物にする」「AI生成と隠して宣伝する」「同じ動画を複数企業に提供する」といったケースでは、別途ライセンスや契約確認が必要になります。
これは再配布や販売、広告素材としての使い方によって扱いが変わってくるため、商用利用範囲であっても慎重な管理が求められます。
安心して使うためにやるべきこと
まずは有料プランに加入し、公式に商用利用が許可されていることを確実にします。
次に、プロンプト設計で第三者の権利を侵害しないよう注意し、問題になりやすい素材は使用しないようにします。
さらに、広告やプロモーションに使う際には「この動画はAIで生成されました」と明示し、誤認を防ぎ信頼性を高めましょう。
最後に、万が一再配布や販売、法人案件で使う場合には、別途ライセンス確認や契約締結を行うとより安全に使えます。
\無料クレジットプレゼント中!今なら動画が無料で生成できる!/
の料金体系や使い方を徹底解説!使ってみた感想も詳しく解説!-300x158.png)
の料金体系や使い方を徹底解説!使ってみた感想も詳しく解説!-300x158.png)
商用利用で具体的にどんなことができるの?
前の章までで、DeeVid AIは商用利用できるツールであることをお伝えしました。
でも一番気になるのは「それで本当に稼げるの?」という部分ですよね。
ここでは、あなたが高品質動画でバズるアカウントを作り、その後どんな形で収益を得られるのかをステップを追ってご案内します。
動画でバズって広告収入
TikTokやYouTube Shorts、Instagramリールのような短尺フォーマットにぴったりのコンテンツをスピーディに投稿できるんです。
AIの自然な映像クオリティと動きのおかげで、初心者にも“バズる”土台が格段に整いやすくなります。
実際に、AI支援でフォロワーや再生数が増えたという声も投稿界隈で聞かれるようになっています。
そして今、トレンドの波に乗ることが、バズへつながる鍵になります。バズれば広告収入がはいるようになります。
実際に、最近SNSで大ヒットしているのは「猫がオリンピック飛び込みをする短尺動画」のような、思わず固まるほどインパクトあるコンテンツです。
これはHailuo aji 02というAIモデルを使って生成されたもので、毛並みや水しぶきの動きが本当にリアル。
もし、本気でバズってマネタイズしたいなら縦スクロールでも視線を確実に止める、5~10秒くらいの短尺形式が特に効果的です。
こうしたユニーク×リアルなトレンドを活かせば、ただ量産するだけではなく、注目されやすい動画が作れますよね。
スポンサー案件もゲットできる
前章でフォロワーや再生数を伸ばし、AIで高品質な動画を量産すれば、次に目指すのが“スポンサー案件”です。
多くの企業は、顧客と共鳴するクリエイターからのPR投稿に価値を見出しており、一定の視聴実績やエンゲージメントがある人に対してオファーを出す傾向があります 。
TikTokやYouTubeなどのプラットフォーム内でも、ブランドとクリエイターをつなぐ仕組みが整っていて、企業は「フォロワー数」「再生回数」「内容の質」「アカウントの世界観」などを見て、最適なクリエイターにスポンサー依頼を送ります 。
DeeVid AIで生成された動画がきれいでプロっぽく、ストーリー性やブランドとの相性がいいと、企業担当者が「ここなら安心して任せられる」と感じやすくなります。
その結果、商品紹介やブランドPRを行うスポンサー案件を獲得しやすくなり、1件あたり数万円から数十万円の報酬につながるケースも珍しくありません 。
アフィリエイトで確実な収入!
スポンサー案件によって企業との信頼が築かれると、視聴者の購買意欲も高まるようになります。
その流れに合わせて、動画の説明欄やキャプションにA8.netで提携した「AI関連グッズ」や「動画生成ツール」のリンクを貼っておくと、視聴者がそのリンクを経由して購入や申し込みをすると報酬が得られる仕組みになるんです。
A8.netは広告主数が約26,500社、メディア会員数は350万を超える、日本最大級のASPとして知られています。
この中には「AIスマートリング」や「動画マーケティングスクール」など、AIツール関連の商品プログラムも多く、ランキング上位に入る案件も頻繁です 。
たとえば「AI動画生成ツールの仕組みを解説する実演動画」を投稿し、その説明欄に紹介リンクを貼っておくと、視聴者が興味をもって購入につながりやすくなります。
リンク経由で成果が発生すると、A8.netでは通常、成果が確定してから翌々月15日に振込があります。また「セルフバック」など即時支払が可能な制度もあるので、比較的早く報酬を受け取れるんです。
こうして「バズ→スポンサー案件→アフィリエイト収益」という流れを構築すれば、AI動画クリエイターとして安定的に収益を得られる仕組みが自然にできあがります。
\無料クレジットプレゼント中!今なら動画が無料で生成できる!/
商用利用でも「絶対にできないこと」を理解しておこう
前段で「有料プランなら商用利用OK」とご紹介しましたが、一方でこれはやっちゃダメという例外もありますよね。
こうしたケースを把握しておかないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあるんです。
ここでは、特に注意すべき「禁止事項」をじっくり解説しますね。
① キャラクター・ブランドの著作権侵害は絶対NG
アニメキャラや有名ブランドのロゴなど、著作権や商標で保護されたものをプロンプトに使うのは避けましょう。
プラットフォーム上では「キャラクター生成OK」と表示されていても、商用利用でそれを使うと法的な責任を問われる可能性があります。
AI生成だからといって安全、という誤解は危険です。
② 作成動画をそのまま販売・配布は要ライセンス
ストック映像サイトで販売したり、有料教材としてそのまま配布したりする行為は商用利用の範囲外となりやすいです。
有料プランは「使用許可」なので、素材そのものを商品として再配布・転売する場合には別途ライセンス取得が必要です。
ただ表示されている商用利用OKで全部カバーされるわけではない点にご注意ください。
③ AI生成を隠して使うのは法的リスクが高い
「自社撮影です」と偽って利用してしまうと、不当表示や不正競争防止法に問われる可能性があります。
広告やSNS投稿で使用する際は、AIであることを広告文やキャプションにも明示するのが信頼の第一歩です。
タグだけ付けて安心ではなく、視聴者に伝わる位置でしっかり明記することが求められます。
\無料クレジットプレゼント中!今なら動画が無料で生成できる!/
DeeVid AIの登録方法
まず試してみたい!って人に、無料プランの使い方を解説していきます。無料プランの登録後すぐに使えるようになります。


グーグルのアカウントがあればすぐにログインできます。
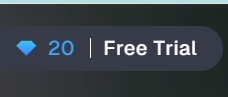
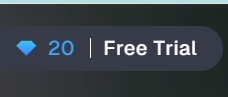
最初のログインでは20クレジットが付いてきます。


まずは画像を選んで動画生成してみましょう。テキストからの動画生成は20クレジット消費して無料動画性世いが1回しかできません。
なので画像から動画生成するのがおすすめです。
\無料クレジットプレゼント中!今なら動画が無料で生成できる!/
まとめ
DeeVid AIは商用利用が可能であると公式に明言されており、商用ベースで動画を収益化する道筋がしっかり整っています。
まず、TikTokやYouTube Shorts、Instagramリールといった短尺縦動画がサクサク作れる点が魅力です。
これによって、再生数が伸びれば広告収入へとつながる「バズ→収益」の第一歩が踏み出せる構造が完成します。
次に、こうして信頼と実績を積むことで、企業からスポンサー依頼が来る可能性がでてきます。ここまでいけば軽くインフルエンサーですね。
\無料クレジットプレゼント中!今なら動画が無料で生成できる!/
の料金体系や使い方を徹底解説!使ってみた感想も詳しく解説!-300x158.png)
の料金体系や使い方を徹底解説!使ってみた感想も詳しく解説!-300x158.png)
















