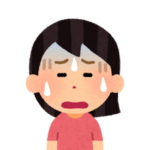
Deevid AIってよく聞くけど、そもそもどんなツールなの?危険じゃない?
まず、DeeVid AIを使う前に「本当に安全なのか」「どこの国のサービスなのか」はしっかり知っておきたいですよね。
結論から言うと、DeeVid AIはきちんと運営実態のある安全性の高いツールです。



私自身も登録して、毎日のように動画生成に使っています。
なぜDeevidAIって安全といえるのか?この記事では、そんな不安をまるっと解消できるよう、ヘビーユーザーの視点で分かりやすくご紹介していきます。
\年間プランが今だけ29%オフ/
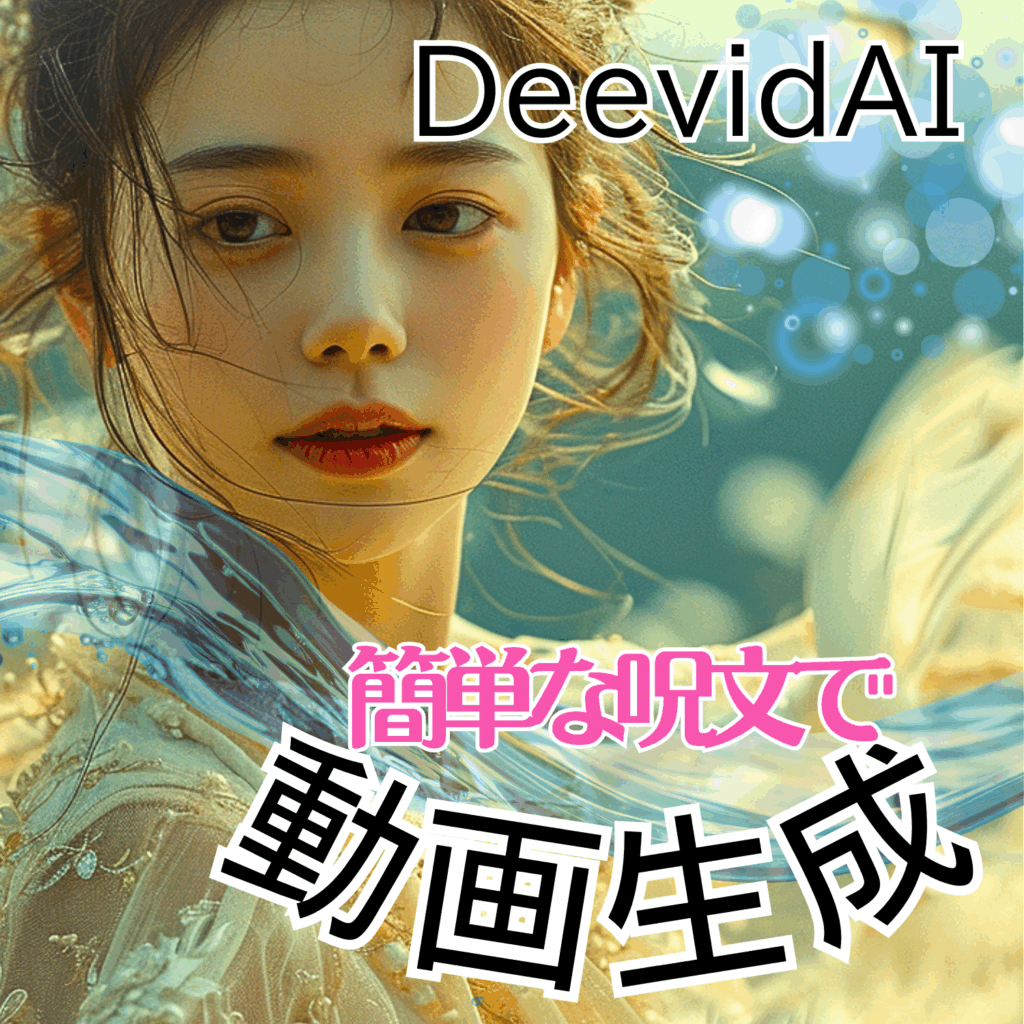
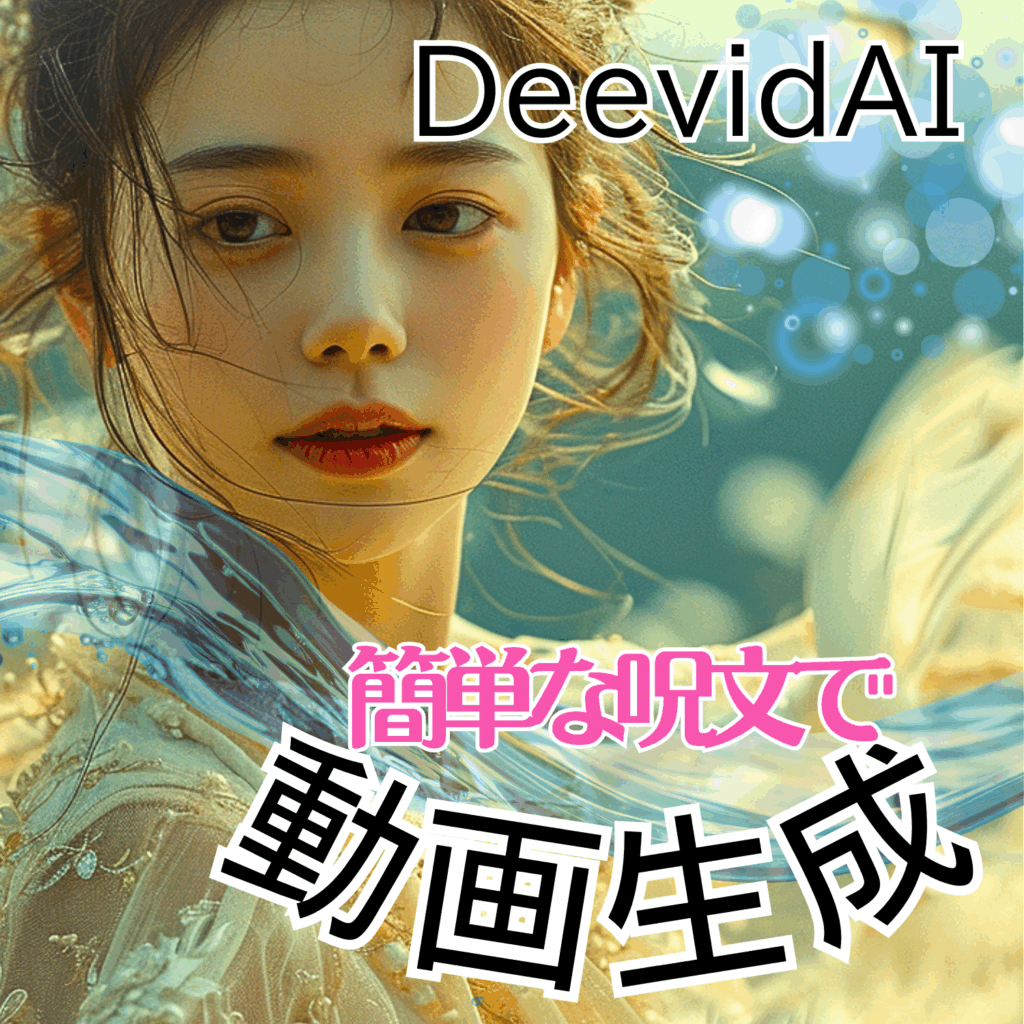


Deevid AI はどこの国のツール?開発元の所在地を徹底リサーチ


まず、Deevid AI がどこの国で作られたのかを深掘りしていきます。



「海外製ってちょっと不安…」というあなたの気持ち、すごくわかります。
どんなツールを使うにしても運営会社や所在地については、曖昧なままにしないことが大切です。わたしも契約前に徹底的に調べてみました。
①本社や法人名は?
②どのくらいの規模なの?
③サービス内容は?
詳細表
まずは、Deevid AI の会社概要や設立年など詳細情報を表にしてわかりやすくしています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開発国・本社所在地 | シンガポール・ラッフルズプレイス(One Raffles Place) |
| 法人名 | Deevid AI Ltd.(正式法人名が公表されている) |
| 設立年 | 2024年(比較的新興ながら公式発表・透明性あり) |
| 従業員数 | 約50〜249名(中規模スタートアップ) |
| AIサービス展開 | 動画生成以外に「text‑to‑video」「image‑to‑video」「video‑to‑video」「AI Ad Generator」など多機能対応 |
| データ安全性対策 | 入力画像・動画は暗号化処理、第三者提供なし。悪用防止・有害生成を抑制する対策あり |
| SSL対応 | 公式サイトはSSL暗号化対応なので、安全にアクセス可能 |
| 商用利用 | 商用OKで、広告やSNS等で収益化に使えるガイドラインあり |
| テンプレート多様性 | テキスト/画像/動画など複数の入力形式に対応し、1分以内で自動生成可能 |
本社や法人名は?
Deevid AIは『Deevid AI Ltd.』の正式な法人名で、企業情報サイトTechBehemothsにも同名で登録されています。
本社はシンガポール、ラッフルズプレイスにある高層ビル「One Raffles Place」の21階に所在していると情報が一致しています。
法人登記と住所が明示されていることで「本当に存在する会社なのかな…?」という不安が自然と消えていきますよね。
透明性がある企業は、それだけで安心感が違うものです。
どのくらいの規模なの?
Deevid AIの設立は2024年と比較的新しく、まだスタートアップの色合いが濃い企業です。



将来を見据え、現在AI関連の会社が続々と設立されています
しかしTechBehemothsによると、従業員数が50~249名とされており、ないがしろにされやすいサポート体制にもちゃんと人手があると思えました。
「小さすぎてすぐ潰れちゃうんじゃ?」という心配も、この規模ならかなり信頼がもてそうですよね。
また、社員がそれだけいる企業なら、継続的な開発や問い合わせ対応も期待できますよね。
\ここから👇無料登録で20クレジットもらえる!今だけ/
\セクシー系の画像が生成できる唯一のAIツール/
Deevid AIは怪しい?詐欺ではない根拠と調べた事実
正直「聞いたことない会社だから不安…」って思うの、すごくわかります。
でも調べてみると、安心して使える証拠がしっかりありましたね。



この時点で安心できた!という方はコチラから利用可能です→DeevidAI
ここでは「怪しさゼロ」に感じた理由を、細かくご紹介しますね。
①公式サイトはSSL対応で通信が保護
②会社情報やプライバシーポリシー
③サービス利用者が世界中にいる
④開発チームは実名で実績も公開されている
⑤TwitterやDiscordなどのコミュニティ活動
① 公式サイトはSSL対応で通信が保護されている
DeevidaiのサイトURLは「https://」で始まっており、SSLによる暗号化通信がしっかり施されています。
これは、入力したテキストやアップロードされた画像・動画が安全に扱われることを意味しています。
暗号化されていないサイトとは違って、個人情報漏洩のリスクが大幅に低減されますよね。
公式にも「securely processed」と明記されており、セキュリティへの配慮を可視化しています。
② 会社情報やプライバシーポリシーが隅々まで明記されている
公式サイトのフッターには「Privacy Policy」「Terms and Conditions」「Refund Policy」などが網羅されていて、コンテンツに齟齬なく細かい内容まで記載されています。
個人情報の扱いや返金規定、利用規約などが明示されていて、利用前に納得できる安心感がありますよね。
ユーザーとして「どう扱われるのか」を把握できるのは大きな信頼材料だと感じました。
③ サービス利用者が世界中にいて実際に使用されている
英語圏のフォーラムやRedditでは「AI video generator」としてDeevidaiの名前を目にします。
実際に「使ったよ」「こんな動画できた」といったリアルな書き込みが多数あり、実在ユーザーの存在が伺えます。
これは単なる宣伝ではなく、信頼できる第三者の視点として非常に説得力がありますよね。
④ 開発チームは実名で実績も公開されている
Deevidaiを支える開発者や運営者は、公式ブログやプレスリリースに名前や経歴付きで登場しています。
他のAIプロジェクトでの実績も書かれていて、「誰が、何を作っているのか」がしっかり見える状態です。



匿名運営のサービスとは違い、顔や名前が出ていることで、信頼感が格段に増しますよね。
⑤ TwitterやDiscordなどのコミュニティ活動が活発に行われている
公式Twitter(X)では最新の生成サンプルやチュートリアル投稿が定期的に行われています。
たとえば「AI meets Classic Art! …」といった投稿もあり、ユーザーとの交流にも積極的です。
Discordコミュニティにもユーザーが集まっていて、情報交換や質問対応などが活発であることから、運営体制の健全さが伝わります。


\ここから👇無料登録で20クレジットもらえる!今だけ/
\セクシー系の画像が生成できる唯一のAIツール/


DeeVid AIでどんな未来になる?実際に使った人の成果を公開
動画生成ツールはとても便利ですが、大事なのは「使ってどんな未来になるのか」です。機能の説明だけでは、なかなか申し込みの決断はできませんよね。
ここでは、実際にDeeVid AIを使って収益化や発信力アップにつながった例を紹介します。あなたが使った時の未来が、少しでも想像しやすくなれば嬉しいです。
① 初心者でも収益化できた例。動画未経験から月3万円達成
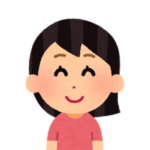
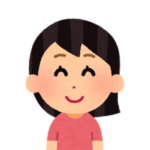
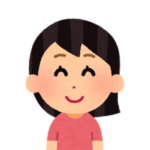
私は、動画制作経験ゼロの状態からスタートしました。人気の動物動画が簡単につくれるし、自分のペットをキャラにして動画をつくるのがおすすめ
最初の頃は生成した動画をSNSに投稿していただけですが、続けるうちにフォロワーが増え、企業から商品紹介の依頼が届くようになりました。
依頼を受けて制作した動画は、1本あたり五千円からスタートし、投稿回数が増えるほど単価もアップしていきました。
現在は月に三万円ほどの収益になり、副業として安定しています。始めた頃の不安な気持ちが、今では達成感と自信に変わったそうです。
② フォロワーゼロから半年で案件依頼に繋がった例



「動画制作を仕事にしたい」という目標があったのですがDeevidAIは一貫性が出せてアニメ動画が簡単につくれました。
SNS投稿を続けることで作品集として役立ち、半年ほどで企業から直接連絡が届いたそうです。
一番最初の依頼単価は八千円ほどでしたが、現在は三万円以上の案件も受けられるようになっています。
動画制作の仕事に挑戦したい人にとって、DeeVid AIは最初の一歩を後押ししてくれる存在になります。
\年間プランが今だけ29%オフ/
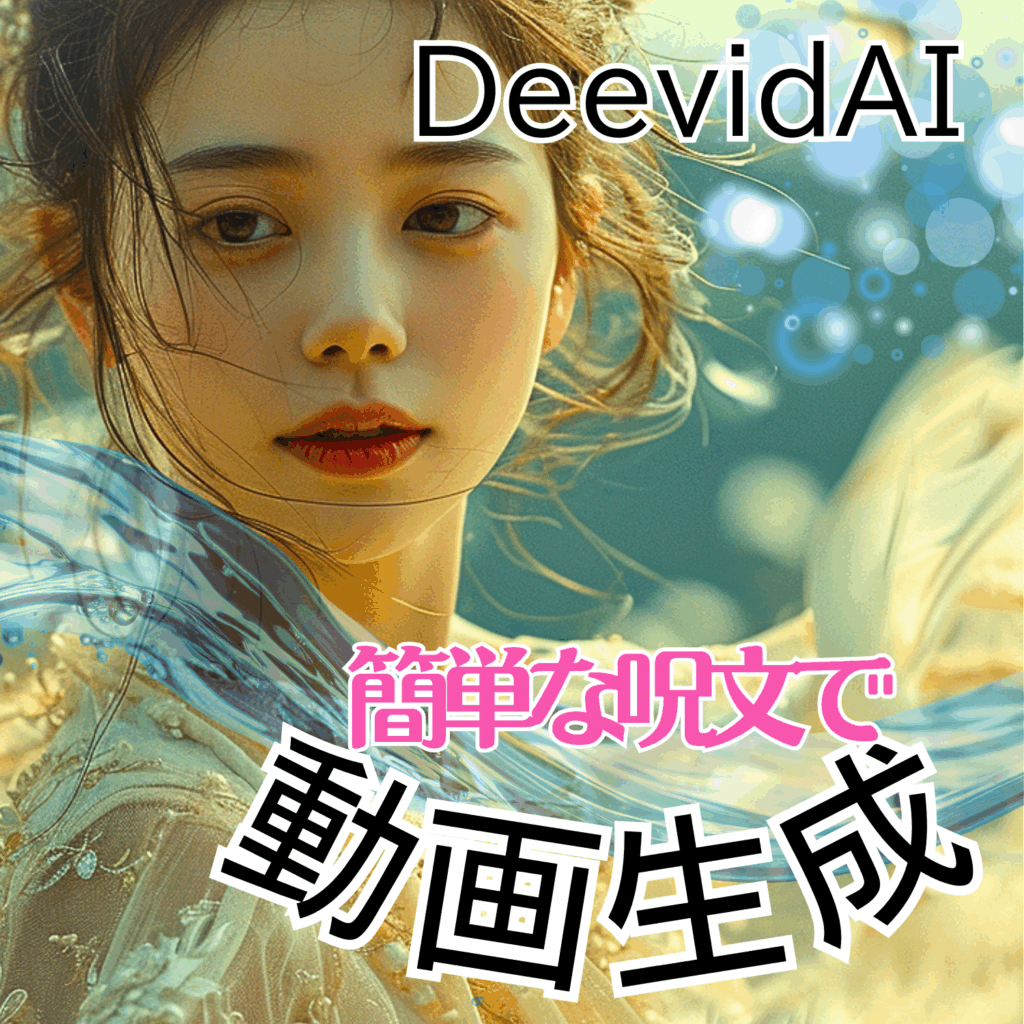
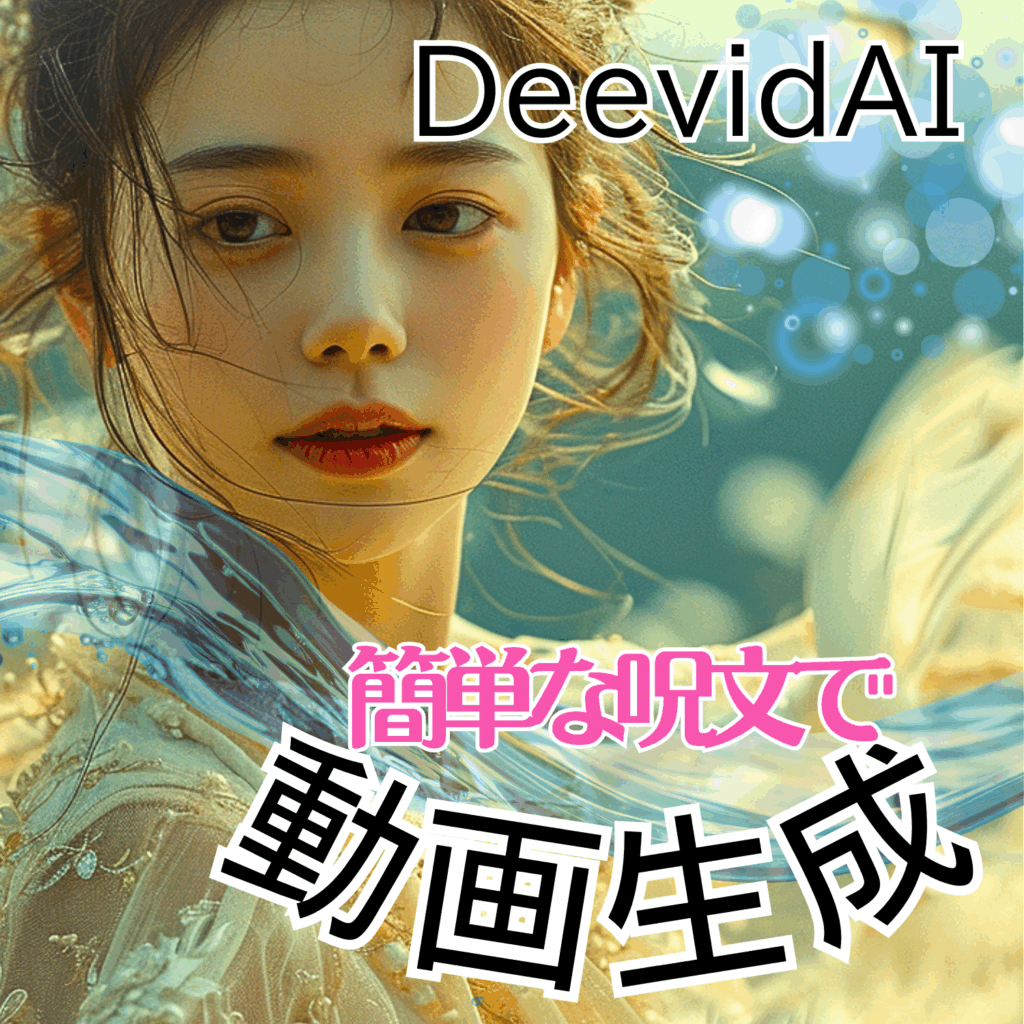
Deevid AIとは?どんなツールなのかをわかりやすく解説


『DeeVid AI』を使う前に、まずはこのAIが『何をしてくれるツールなのか』をしっかり理解しておきましょう。
なんとなく「動画を作るAIでしょ?」と思っていた方も、実際の機能や使い方を知ると、きっと想像以上に幅広くて驚くはずです。



このツールは単なる『AIで映像が作れる』というだけではないです
Deevid AIの魅力を一言で言うなら、『プロ品質の動画を、誰でもサクッと自動で作れる』こと。
しかも、見た目のクオリティが高いだけじゃなくて、キャラの表情や自然な動きまでもがしっかりと考えられているんです。



こういったSNSで人気のショート動画、びっくりするくらい簡単にできます!



ショート動画やリールで収益化を狙う方は1カ月100本以上の動画が生成できるプロプランを契約するといいです
では、私が実際に使ってみて感じた機能のポイントを、順番にご紹介していきますね。
①動画生成の質が高いと評判
②キャラクターの一貫性を保てるAI制御
③操作が簡単で初心者でも扱いやすい
④商用利用もOKなAI動画ツール
⑤がっつり自分のAIアニメもつくれる
①動画生成の質が高いと評判
まず最初に驚いたのは、出来上がった動画のクオリティの高さでした。



散々動画再生ツールを使いこなしてきた私でもこれには感動
動きがとてもなめらかで、背景の美しさやキャラクターの描写も細かく、まるで手描きのアニメーションのように仕上がっていたんです。
音声のテンポや口の動きも自然で、ちょっと見ただけではAIで作ったとは思えないレベル。
私自身も「これ、ほんとにAIなの…?」って思わず二度見しました。
特にSNSで投稿するような短尺の動画では、Deevid AIの品質は他のツールと比べても抜きん出ていると思います。
②キャラクターの一貫性を保てるAI制御
AI動画でよくあるのが、シーンごとにキャラクターの顔や髪型が変わってしまうという問題。
でもDeevid AIは『キャラ一貫性』を意識した設計になっていて、同じキャラを何度使っても崩れにくいんです。
これは連続性のある物語を作りたい人にはとってもありがたい機能ですよね。
しかも、プロンプトのコツをつかめばさらに安定します。
ちょっとした調整で、見た目をしっかり固定できるのは本当に便利でした。
③操作が簡単で初心者でも扱いやすい
ぶっちゃけますが、中には操作が難しくてうんざりするツールもあります。
でもDeevid AIは本当に直感的に操作できて、テンプレートにテキストを入れていくだけで、あっという間に動画が完成します。
しかも、UIがとてもシンプルで、どこを押せばいいか迷うことがありませんでした。
正直、動画編集ソフトよりもずっとラク。
説明書なんて読まなくてもサクサク動かせるので、初心者でも安心して使えますよ。
④がっつり自分のAIアニメもつくれる
ちなみに、DeevidAIだとこちらのようなオリジナルAIアニメ映像がたった3時間ほどでつくれます。
音が出ますので注意です。
この一貫性を持たせた女性のカットもDeevidAIが1番得意だと思います。



一貫性をもたせるということが意外とほかのツールでは難しいんです
そのほか、数カットKlingとDomoAIも使ってます。セリフを入れたい場合はDomoAI、戦闘シーンはKlingAIで動かすのがおすすめです。
こんな映像がつくれるんですから、ぜひ映像やアニメを作ってみたい方にはすぐにでも使ってほしいおすすめツールです。


\年間プランが今だけ29%オフ/
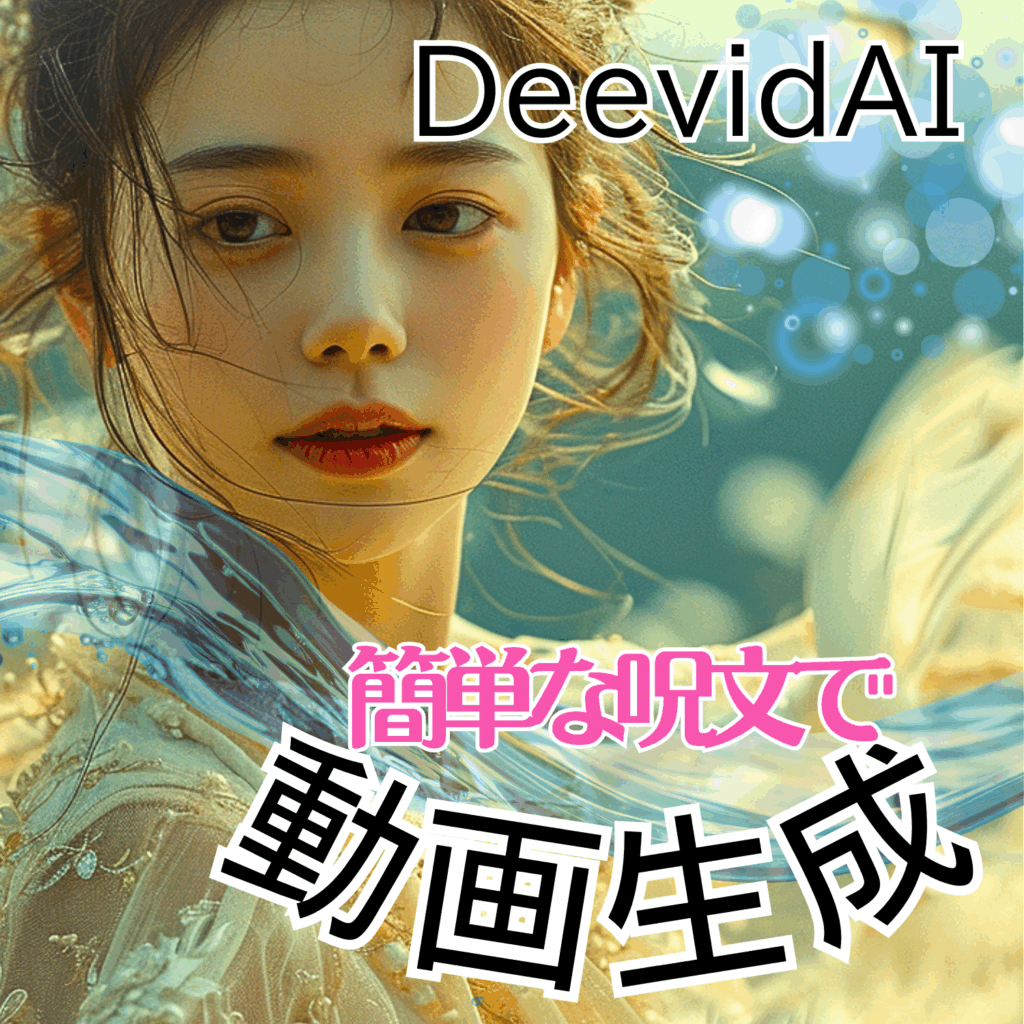
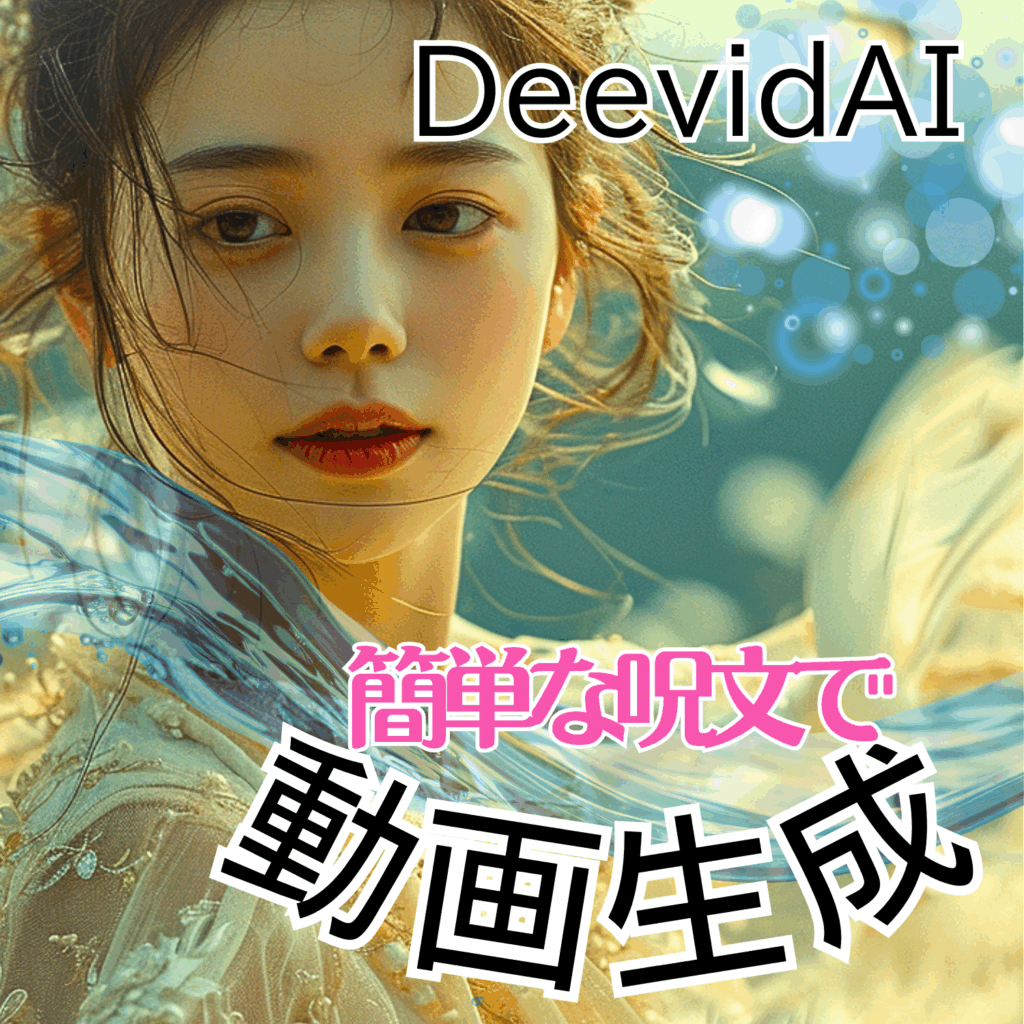


- 【マネタイズ】AI美女の稼ぎ方を教えます!おすすめツールからマネタイズまで徹底解説していくよ!
- 【動画AI生成】Domo AI 動画生成ツールの口コミ・評価まとめ
- 動画生成AIのおすすめランキングTOP14【2025年最新版】私が最終的に使い続けているツールはこれ!
- 画像生成AIを使ってインスタで月10万円稼ぐ方法!初心者でも3か月で収益が得られる!
- 生成AIで副業するならどのスクールがおすすめ?未経験から副業を学べるスクール7選!
Deevid AIは商用利用できる?
AI動画でマネタイズしたい方にとって、商用利用ができるかどうかはとても大切なポイントですよね。
公式サイトにも商用目的の利用が可能であることが明記されており、YouTubeの広告収益やSNSでのプロモーション、案件用の動画制作など、幅広い使い方ができます。
実際に、YouTubeチャンネルの収益化や企業プロモーション動画、オンライン講座のオープニング映像などに活用している例も多く、「コストは抑えたいけれど、クオリティには妥協したくない」という人には相性の良いツールだと感じました。
また、Deevid AIで生成した動画にはクレジット表記の義務がなく、著作権もユーザーに帰属します。
そのため、自分のブランド名で堂々と発信でき、企業案件や商品紹介動画にも安心して使えるのが大きな強みです。
商用利用にあたっては、有料プランへの加入が必須であること、外部素材を使う場合はライセンスに注意すること、そして利用規約やポリシーが更新される可能性があるため定期的に公式サイトを確認すること。
この3点さえ押さえておけば、Deevid AIは「安全に稼ぎに使える」AI動画ツールだと言えます。
\ここから👇無料登録で20クレジットもらえる!今だけ/
まとめ
ここまで見てきたように、Deevid AIはシンガポール拠点の法人が運営している、実在性と透明性の高いAI動画生成プラットフォームです。
本社所在地や法人名、従業員規模、セキュリティ対策、商用利用ポリシーまでしっかり開示されていて、「よく分からない海外ツールで怖い」という不安はかなり薄れるはずです。
私自身もヘビーユーザーとして使い続けていますが、動画のクオリティやキャラの一貫性、操作のしやすさ、安全性のどれを取っても、安心して人にすすめられるレベルだと感じています。
特に、ショート動画やリールで収益化を狙いたい方にとっては、「安全性」と「稼げるポテンシャル」を同時に満たしてくれる貴重なツールです。
もし今、「どこの国のツールか分からなくて不安」「本当に安全に使えるのかな」と迷っているなら、ここまでの内容を確認したうえで、一度触ってみる価値は十分あります。
まずは登録して実際に動画を作ってみて、あなた自身の目で「安心して使えるかどうか」「自分のビジネスや発信に合うかどうか」を確かめてみてくださいね。















