「ゲームプランナーなんてやめとけ」
そんな言葉を耳にして、不安になっていませんか。
確かにゲーム業界には厳しい現実があります。
でも、その裏には“挑戦する人にしか見えない夢”が広がっているのも事実です。
この記事では、なぜゲームプランナーが「やめとけ」と言われるのか、その歴史と理由を解説しながら、成功する人の違いを明らかにします。
そして最後に、未経験からでも夢に近づける具体的な方法を紹介します。
ゲームプランナーはやめとけと言われる理由5選

ゲームプランナーは華やかに見える一方で、「やめとけ」と言われることも少なくありません。
ですが、裏側にある現実を知れば「大変さ=チャンス」に変わる部分もたくさんあるんです。
ここでは5つの理由を整理しながら、その先にある可能性についても見ていきましょう。
① 長時間労働とハードなスケジュール
ゲーム開発は納期が厳しく、時には深夜まで作業が続くこともあります。
体力的にも精神的にも負担が大きく、この大変さから「やめとけ」と言われることがあるのです。
ただし、実力をつけてディレクターやリーダーの立場になれば、自分の裁量で進行をコントロールできるようになります。
 もりんさん
もりんさんつまり「過酷さを経験した先に、働き方を選べる自由」が待っているのです。
② 収入が安定しにくいイメージ
平均年収は350万〜500万円程度ですが、会社やタイトルによって差が大きいのが現実です。
ヒット作を出せなければ収入が伸びにくく、「生活が安定しない」と感じる人もいます。
ですが、ゲームプランナーとして培った企画力や進行管理スキルは他業界でも評価されます。
ITやWebサービスのディレクターに転身して年収700万〜1000万円を狙う人もいるほどです。
つまり「安定しにくい」という言葉の裏には、「実力があれば収入の幅が広がる」という真実も隠れています。
③ 責任の重さにプレッシャーがある
ゲームプランナーはチーム全体をまとめる立場にあるため、仕様書の不備や進行の遅れが大きな影響を及ぼします。
その責任感の重さから「やめとけ」と言われがちです。
ですが、若いうちからリーダー経験を積めるのは大きな強みです。
この経験は将来のキャリアアップやマネジメント職へのステップに直結します。
④ 独学では限界がある
本やネットで学ぶことはできますが、現場で必要なチームワークや改善提案力までは身につきません。
だから「独学では無理」と言われるのです。
逆に言えば、正しい環境で学べば一気に差をつけられるということ。
効率的にスキルを伸ばせば、独学で迷っているライバルを一気に抜け出せます。
⑤ 競争が激しい業界
ゲームプランナーは人気職種なので、志望者が多く競争は激しいです。



「簡単には入れない」と言われるのも事実です。
しかし、差別化できれば一気に抜け出せる世界でもあります。
企画書の完成度やチーム経験を積むことで、ライバルに大きく差をつけられるのです。


ゲームプランナーで成功する人と失敗する人の違い


ゲーム業界に挑戦する人は多いですが、そのすべてが成功するわけではありません。
同じ未経験からスタートしても、大きなプロジェクトを任されるようになる人と、途中で諦めてしまう人に分かれます。
その差はほんの小さな習慣や考え方の積み重ねですが、時間が経つにつれて大きな違いとなって表れるのです。
ここでは、ゲームプランナーとして活躍できる人の特徴と、挫折してしまう人の違いを4つに整理して解説します。
① 学び続ける姿勢
成功するプランナーは「自分にはまだ学ぶことがある」と常に成長を意識しています。
新しいゲームトレンドやAI技術、開発ツールの進化に敏感で、日々吸収を怠りません。
例えば、スマホゲームの急成長期に流れに乗れた人は、運営型タイトルの企画ノウハウを早くから学んで市場で優位に立ちました。
逆に「もう十分知っている」と思ってしまう人は、数年のうちに知識が古びていき、若い世代に追い抜かれてしまいます。
「学び続ける姿勢」こそ、キャリアを長く続ける最大の武器なのです。
② チームをまとめる力
ゲーム開発はプランナー1人の力で完結するものではありません。
プログラマー、デザイナー、サウンド、マーケターなど、多くの人の力を束ねて初めて作品は完成します。
会議で意見がぶつかっても、冷静に落としどころを見つけ、チーム全体を前へ進める力があるのです。
一方で、失敗する人は自己主張ばかりが強く、周囲と対立して孤立しがちです。
結果として「一緒に仕事をしたくない」と思われ、プロジェクトから外されることも珍しくありません。
③ アイデアを形にする力
「こんなゲームを作りたい」と口にするのは誰にでもできます。
成功する人はその思いを企画書や仕様書に落とし込み、誰が読んでも理解できる形にします。
たとえば「冒険RPGを作りたい」だけでは伝わりません。
失敗する人はアイデアを語るだけで終わり、具体的な形にできないために実現のチャンスを逃してしまいます。
④ 知識を補う力
ゲームプランナーには、企画力だけでなく幅広い知識が求められます。
ユーザー分析やKPI設計、UI/UXの理解、収益モデルの設計など、ビジネスの視点まで含まれるのです。
成功する人は、自分に不足している分野を認め、それを外から積極的に学び取ります。
たとえばデータ分析が弱ければ統計の講座を受けたり、UXが苦手なら専門のフィードバックを受けたりして、知識の穴を埋めていきます。
一方、失敗する人は独学にこだわり、同じ場所で足踏みを続けてしまいます。
企画やマネジメントは実践とフィードバックを受けなければ成長しにくいため、やがて限界にぶつかり、夢を諦める人も少なくありません。
だからこそ「正しい環境を選べるかどうか」が、成功と失敗を分ける大きなポイントになるのです。
ゲームプランナーという仕事の魅力とは?
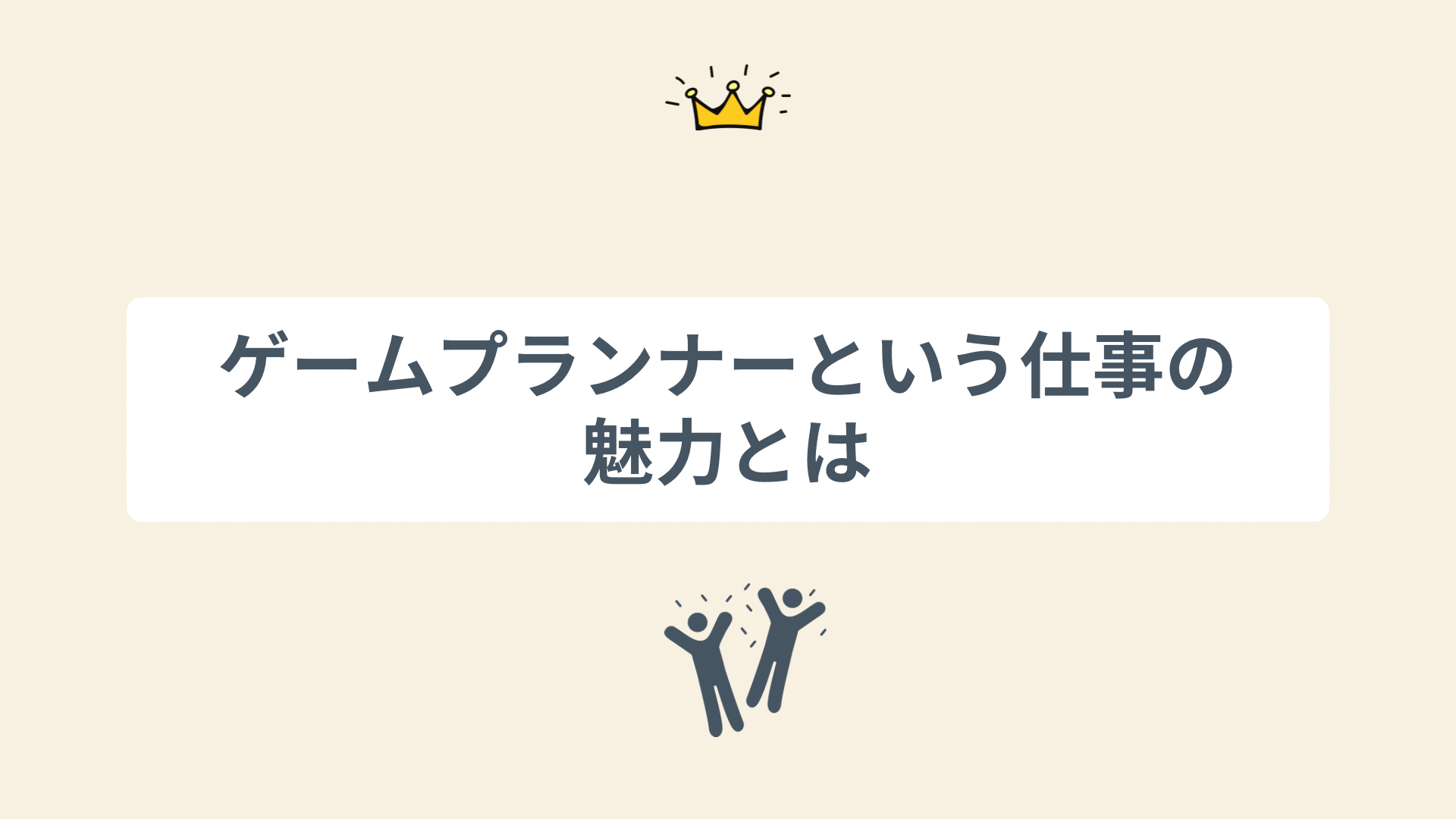
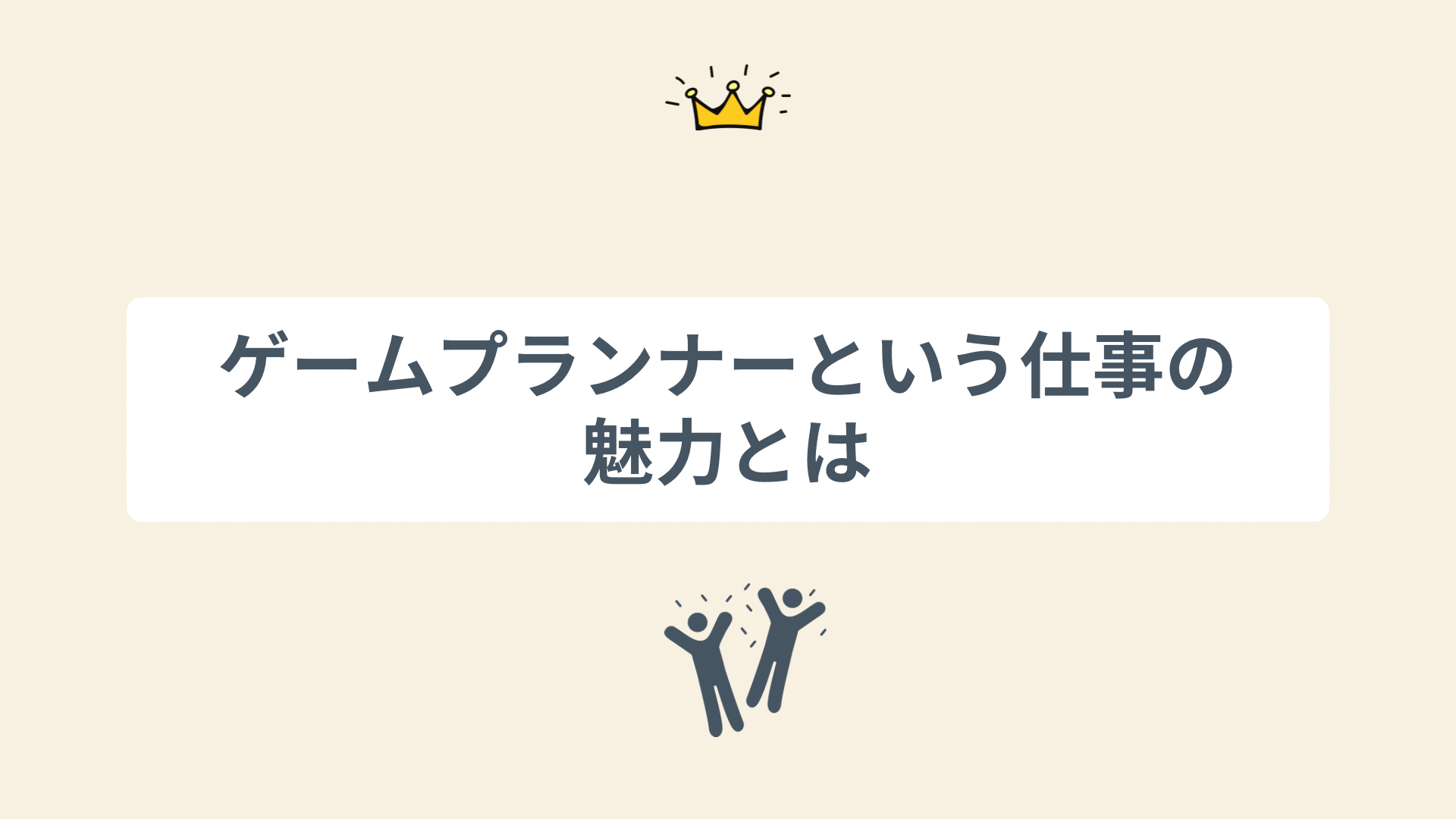
ゲームプランナーには「やめとけ」と言われるような厳しい現実もあります。
しかし、それ以上に人を惹きつける夢や魅力があるからこそ、今も多くの人がこの道を目指しているのです。
ただの安定した仕事ではなく、「自分のアイデアで世界を動かしたい」という強い気持ちを形にできるのが、ゲームプランナーという職業の特別な価値なのです。
ここでは、ゲームプランナーならではの魅力を4つの観点から深掘りして紹介します。
① 自分のアイデアを世界に届けられる
ゲームプランナーは、頭の中で思い描いたアイデアを形にして、多くの人に体験してもらうことができます。
キャラクターの動き、物語の展開、ゲームバランスの調整など、自分が考えた企画がそのまま作品に反映され、世界中のプレイヤーに届くのです。
たとえば任天堂の宮本茂さんは、子供の頃に野山を探検した体験をヒントに「ゼルダの伝説」を生み出しました。
自分の原体験が作品となり、数十年にわたり遊ばれ続けている。これは「アイデアが人類共通の楽しみになる」というゲームプランナーの魅力を象徴しています。
自分の発想が何百万人もの心に残るかもしれない——そう考えるだけで胸が高鳴りますよね。
② 成果がキャリアと収入に直結する
ゲームプランナーのもう一つの魅力は、努力が形となって評価されることです。
多くの仕事では成果が見えにくいですが、ゲームプランナーは作品という目に見える形で結果を出すことができます。
そして、その作品がヒットすれば次の大きなプロジェクトを任され、キャリアも収入も大きく伸びていきます。
稲船敬二さんは「ロックマン」を成功させ、その後に多数の大作を担当し、プロデューサーとしても高い評価を得ました。
このように、実績を積み重ねれば年収1000万円を超える道もあり、「成果が直接キャリアにつながる」という夢のある構造になっています。
自分の名前がスタッフロールに流れ、次の大作を任される瞬間。これこそゲームプランナーにしか味わえない醍醐味です。
③ プレイヤーの心を動かす体験を作れる
ゲームは単なる娯楽ではなく、人の心を強く動かす体験を届けるものです。
プランナーは「どんな体験をしてもらいたいか」を考え抜き、シナリオやシステムを設計していきます。
「どうぶつの森」シリーズを手がけた京極あやさんは、戦いや競争ではなく“日常の温かさ”をテーマにしたゲームを世に送り出しました。
その作品はコロナ禍において世界中で支持され、人々の生活に癒やしを与える存在となりました。
ゲームを通して誰かの心を支えられる。そんな役割を担えるのは、ゲームプランナーという仕事の特別な魅力です。
④ 時代を形づくる存在になれる
ゲームプランナーの仕事は、単なる一作品にとどまりません。
時には新しい遊び方を生み出し、業界全体の方向性を変えてしまうほどの力を持っています。
任天堂の高橋伸也さんは、ゼルダシリーズやNintendo Switchの企画に関わり、その発想力で世界中のプレイヤーの体験を刷新しました。
彼のように、一人のプランナーの提案が新しいスタンダードを作り、次世代の流行を決定づけることもあるのです。
つまり、ゲームプランナーは「時代を動かす仕事」でもあるのです。


ゲームプランナーは本当にやめておくべきか?
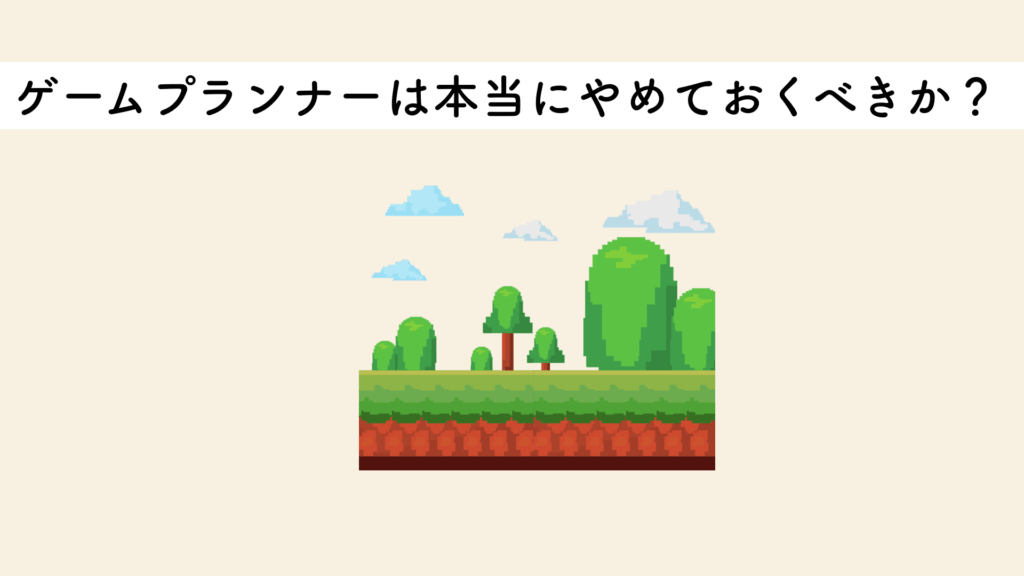
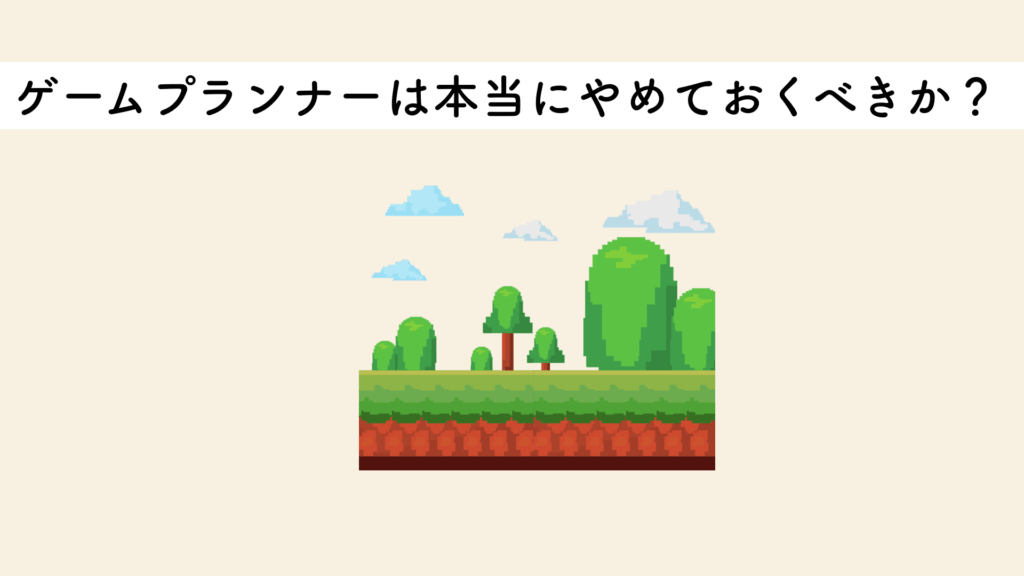
「ゲームプランナーはやめとけ」という声があるのは事実です。
長時間労働や納期のプレッシャー、収入の不安定さ、競争の激しさ……。準備不足のまま飛び込んでしまえば、厳しい現実に押し潰される可能性は高いでしょう。
ですが、これはあくまで一部の人に当てはまる話でもあります。
夢を語るだけで行動しない人、独学に固執して成長の機会を逃す人、チームと協力できない人——こうした人には確かに「やめとけ」と言わざるを得ません。
一方で、常に学び続ける姿勢を持ち、チームをまとめ、アイデアを形にできる力を磨き、そして不足している知識を素直に補える人にとっては大きなチャンスがあります。
そうした人は、自分の発想を世界に広げ、ヒット作を生み、時には時代を動かす存在にすらなれるのです。
つまり「やめとけ」という言葉は全員に向けられたものではありません。
正しい環境を選び、努力を継続できる人にとって、ゲームプランナーはむしろ『夢をつかめる舞台』なのです。
ゲームプランナーに向いている人
ゲームプランナーに向いている人にはいくつかの共通点があります。
ここでは代表的な特徴を紹介します。
① 学び続けることを楽しめる人
ゲーム業界は流れが速く、新しい技術やトレンドが次々に生まれます。
その変化を前向きに受け止め、知識を増やすことを楽しめる人は強い武器を持っています。
学び続ける姿勢が、長く活躍するための大きな力になるのです。
② チームで動くことが好きな人
ゲーム制作は一人で完成させることはできません。
プログラマーやデザイナー、サウンド担当など多くの人と協力しながら進めるため、人と話し合い調整できる人は強みを発揮します。
仲間と作品を作り上げる喜びを感じられる人は、プランナーに向いています。
③ アイデアを形にする粘り強さを持つ人
面白い発想を思いつくだけでなく、それを企画書や仕様書に落とし込み、他人に伝わる形にできることが重要です。
途中で投げ出さずに最後までやりきれる粘り強さを持つ人は、信頼されるプランナーになれます。
④ ユーザーの気持ちを想像できる人
ゲームは遊ぶ人がいて初めて成り立ちます。
プレイヤーがどんな体験を求めているのかを想像できる人は、魅力あるゲームを生み出せます。
「自分が楽しむ」だけではなく「人を楽しませる」という視点を持てることが、プランナーの適性なのです。
ゲームプランナーに向いていない人
ゲームプランナーは誰でも挑戦できる仕事に見えますが、実際には最低限必要な素養があります。
ここでは「このタイプは現場で苦労しやすい」という向いていない人の特徴を3つにまとめました。
① パソコン操作に極端に弱い人
ゲーム開発はパソコン上で進みます。
仕様書の作成だけでなく、UnityやUnreal Engineといった開発環境を使って画面を確認したり、ツールを操作したりする場面も出てきます。
もし「キーボード入力に慣れていない」「ソフトを立ち上げるだけで時間がかかる」というレベルなら、現場で仕事をこなすのは難しいです。
特に最近はデータの入力や数値の調整もプランナーの役割になることが増えているため、基本的なPCリテラシーが欠けている人には厳しい環境になります。
② プログラミングや開発の基本を理解しようとしない人
ゲームプランナーはコードを書く必要はありません。
ですが、プログラマーやデザイナーと会話するには、最低限の開発知識を理解しておく必要があります。
「変数」「ループ」「処理が重い」などの基本概念が全く分からないと、アイデアを出しても「それは技術的に不可能」と却下されることが増えます。
現実的な制約を知らないままでは、チームの信頼を得られません。
技術の基礎を学ぶ気持ちがない人は、プランナーとして成長しづらいのです。
③ ゲームに興味がなく研究を怠る人
プランナーの仕事は「遊ぶ側の気持ち」を理解して企画に落とし込むことです。
そのためには、日頃からさまざまなジャンルのゲームに触れて「何が面白いのか」「どんな改善点があるのか」を研究する習慣が欠かせません。
「ゲームはほとんど遊ばない」「流行も知らない」という人は、ユーザー視点の提案ができず、開発に貢献できません。
ゲームが好きでなければ続かない仕事だからこそ、興味を持てない人には向いていないのです。


ゲームプランナーになる3つの方法
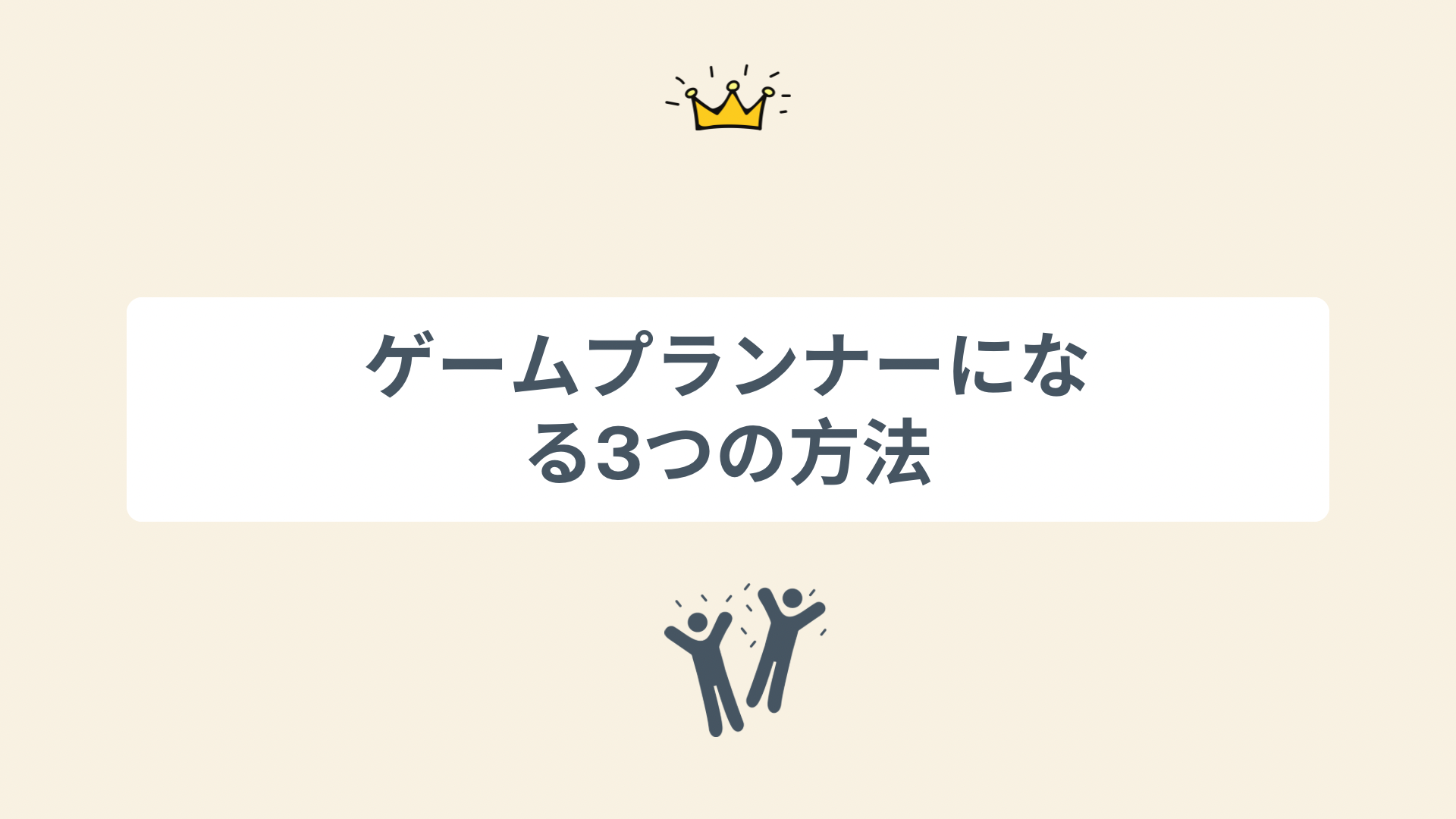
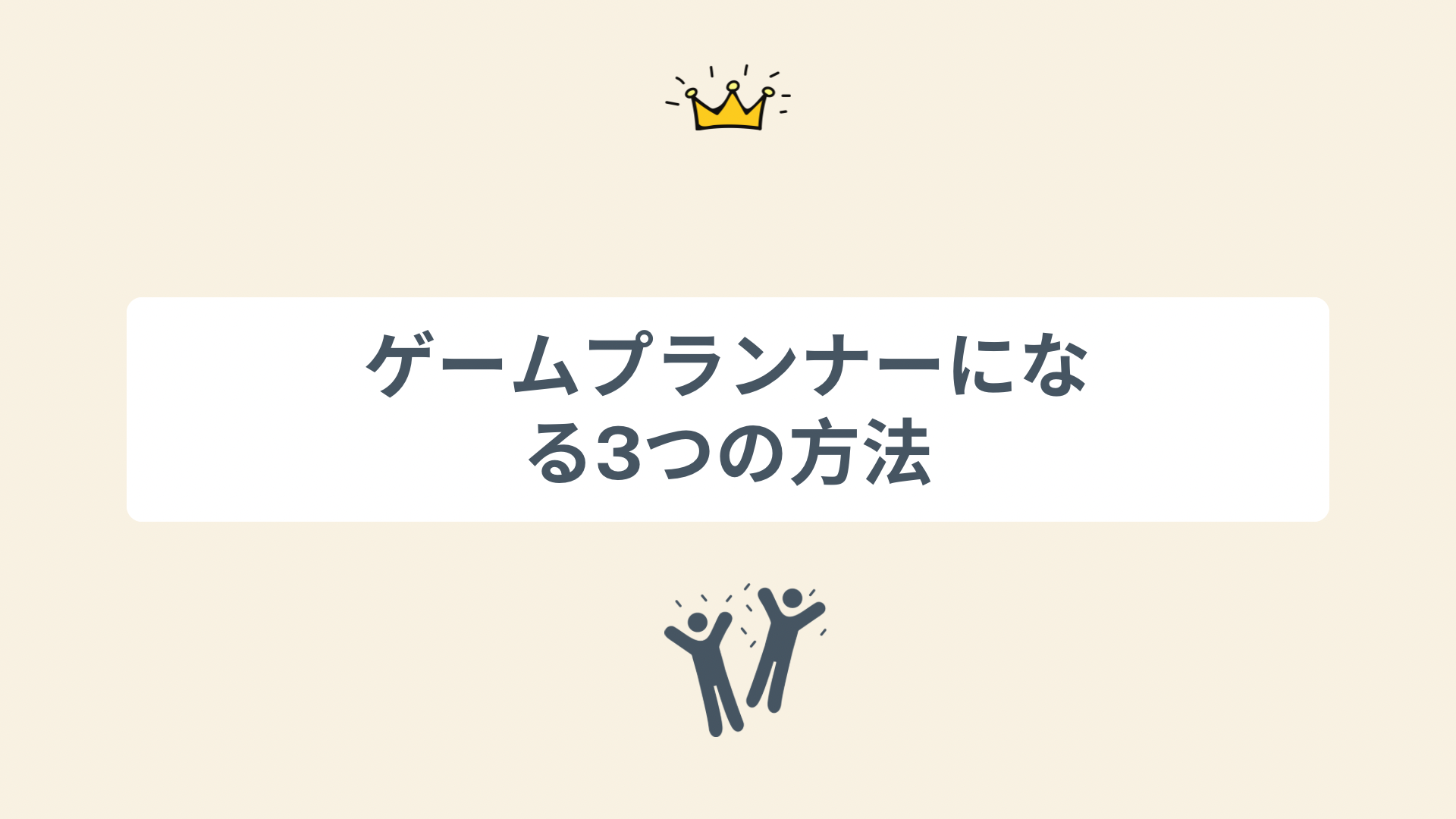
ゲームプランナーを目指すには、まず必要な知識とスキルを身につけることが大切です。
方法はいくつかあり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
ここでは代表的な3つの学び方を整理します。
① 独学で学ぶ
独学はコストをかけずに始められる点が魅力です。
ただし、情報が断片的で体系的に理解しにくく、実際の現場で通用するレベルまで到達するのは難しいのが実情です。
「自己流でやってみたけど、どこかで壁にぶつかる」という人も多い学び方です。
② 無料動画やチュートリアルを利用する
YouTubeなどの無料動画は、今すぐ始められて視覚的に分かりやすいのがメリットです。
ただし、内容の質にはバラつきがあり、最新の情報でない場合もあります。
また、動画を見ただけでは「実際に手を動かして作る経験」が不足しがちで、深い理解にはつながりにくい面もあります。
③ スクールで体系的に学ぶ
本気でゲームプランナーを目指すなら、スクールで学ぶのが最も効率的です。
企画の作り方からチーム制作まで一通り学べる環境は、独学や無料動画にはありません。
ただ、日本ではプログラミングやデザインのスクールは多いものの、ゲームプランナーに特化した講座は非常に少ないのが現実です。
だからこそ『GPCゲームオンラインスクール』のように、未経験から実践的に学べる場は貴重な選択肢になるのです。
まとめ
ゲームプランナーは「やめとけ」と言われる厳しさもあります。
しかし、その一方で自分のアイデアを形にし、世界中の人に遊んでもらえるという大きな夢があります。
ヒット作を生み出せばキャリアも広がり、時には時代を動かす存在になれるのです。
もちろん簡単な道ではありません。
パソコン操作や基礎的な知識が必要で、チームをまとめる力や粘り強さも求められます。
けれども、正しい学び方を選び、努力を重ねれば、誰にでもチャンスはあります。
ゲームが好きで「自分の発想を世に出したい」と思うなら、その気持ちを大切にしてください。
未来のヒットタイトルに、自分の名前が載る日が来るかもしれません。















